観光や移住が活発になるほど街は活気づきますよね。しかし同時に、家賃の上昇や日用品店の減少など、在住者視点では困りごとも増えます。日本では東京の下町や京都などで、ジェントリフィケーション(街の高級化)が問題になっているという記事をみかけますが、こちらメキシコでも、メキシコシティ(ローマ/コンデサ周辺)やオアハカ、トゥルム、サン・ミゲル・デ・アジェンデなどの観光都市で、問題になっています。
ジェントリフィケーションとは?
- 定義:低家賃で暮らしていた住民や店舗が、再開発・観光・短期賃貸化・高所得層流入などを背景に、家賃上昇や用途変更で押し出される現象。
- きっかけの例:民泊や短期賃貸の拡大、カフェ/ギャラリーの増加、都心回帰、インフラ整備、海外・外資マネーの流入、デジタルノマド。
- 影響:住まいの負担増、日用品店の減少、生活の観光化、コミュニティの弱体化など。
ジェントリフィケーションと観光公害は、どちらも都市や観光地の負の側面を指す言葉ですが、焦点が少し違います。
●ジェントリフィケーション=開発による住民の追い出しや文化の変容
●観光公害=観光客の集中による地域住民の生活への悪影響
中でも「ツーリズム・ジェントリフィケーション」は、観光開発が不動産価格を高騰させ、元々の住民が立ち退きを余儀なくされる現象を指し、観光公害の一種とも捉えられます
メキシコでいま何が起きているか
メキシコシティ
ローマ/コンデサや中心部の再評価が進み、短期賃貸やコリビング、リノベ物件が増加。飲食・クリエイティブ産業が活発化する一方、長年の住民の家賃負担が重くなっています。
観光都市
世界的な人気上昇により、歴史地区のホテル化/商業化が進展。季節要因で相場が跳ねやすく、地域の生活機能が圧迫される場面もあります。
オアハカ、トゥルム、プラヤ・デル・カルメン、サン・ミゲル・デ・アジェンデ、メリダなど
産業都市
モンテレイ、ケレタロ等の産業都市では、投資・雇用拡大で新築供給が追いつかず賃料が上昇。短期駐在層やハイエンド需要が局所的に相場を押し上げるケースも見られます。
補足:“観光型”と“産業成長型”の二つの圧力があり、どちらも住居費上昇につながりやすい構造があります。
日本では
東京の下町
清澄白河/蔵前/浅草/谷根千など、東京の下町と言われるエリアでは、カフェやギャラリー、リノベ物件の増加で人気が上昇しています。“住める賃料”だった地域が“憧れ価格”へと変化し、古い商店の減少も指摘されています。
渋谷周辺や湾岸
再開発・オフィス需要・タワーマンション供給が重なり、地価・賃料が上振れ。個人商店が入れ替わる動きも加速しています。
京都
歴史的景観と観光人気の高さから、町家の宿泊施設化や民泊の影響が議論に。生活の場と観光地の境界が曖昧になりがちです。
地方都市(福岡、札幌、名古屋など)
創業支援やクリエイティブ地区の形成が進む一方で、元住民・小規模店舗の居場所が狭まる懸念もあります。
メキシコと日本 共通点と相違点
| 観点 | メキシコ | 日本 |
|---|---|---|
| 主な圧力 | 観光+産業成長+海外移住(デジタルノマド含む) | 観光+都心回帰+再開発(人口減だが局所的に高騰) |
| 住宅市場 | 新築供給が追いつかず上昇しやすい都市あり | 空き家活用もあるが、人気エリアは高騰 |
| 商店 | 観光・外食が伸び、日用品店が減るケース | チェーン化・観光化で個人店が退く場合 |
| 規制 | 短期賃貸の規制や税制は都市で差 | 民泊・用途地域・景観条例など比較的整備 |
| 体感 | 季節やイベントで相場が振れやすい観光地が多い | 年単位でじわりと変化、再開発で局所的に急変 |
旅行者・移住者ができること
- 規則を守る:民泊のハウスルール、騒音・ゴミ出しなど地域ルールを最優先。
- ローカルにお金を落とす:スーパーマーケット、八百屋、地元のコーヒー焙煎店など日常店を選ぶ。
- 長期の視点:短期賃貸だけでなく、長期賃貸や共助の仕組みに参加(自治会、清掃、寄付など)。
- 言語と礼儀:簡単な現地語(メキシコならスペイン語、日本なら日本語)の挨拶やお願い表現を覚え、摩擦を未然に防ぐ。
私は今は移住者でもあり旅行をするときは旅行者にも当てはまります。どれも、本当に大切なこと。言語面などすぐには難しい面もあるけれど、ルールを守ることなどは基本中の基本。郷に入っては郷に従えですね。特に日本だと、日本人が英語を話さないのを外国人に利用されていると感じてしまうこともあります。
まとめ——「観光と暮らし」を両立させるために
街が注目されること自体はチャンスです。しかし、その恩恵が地元にも還元され、長く暮らせる仕組みがなければ、街の魅力はやがて痩せてしまいます。旅行者・移住者・事業者・自治体が、それぞれの立場で一歩ずつ。私たち一人ひとりの選択が、街の将来を静かに形づくります。
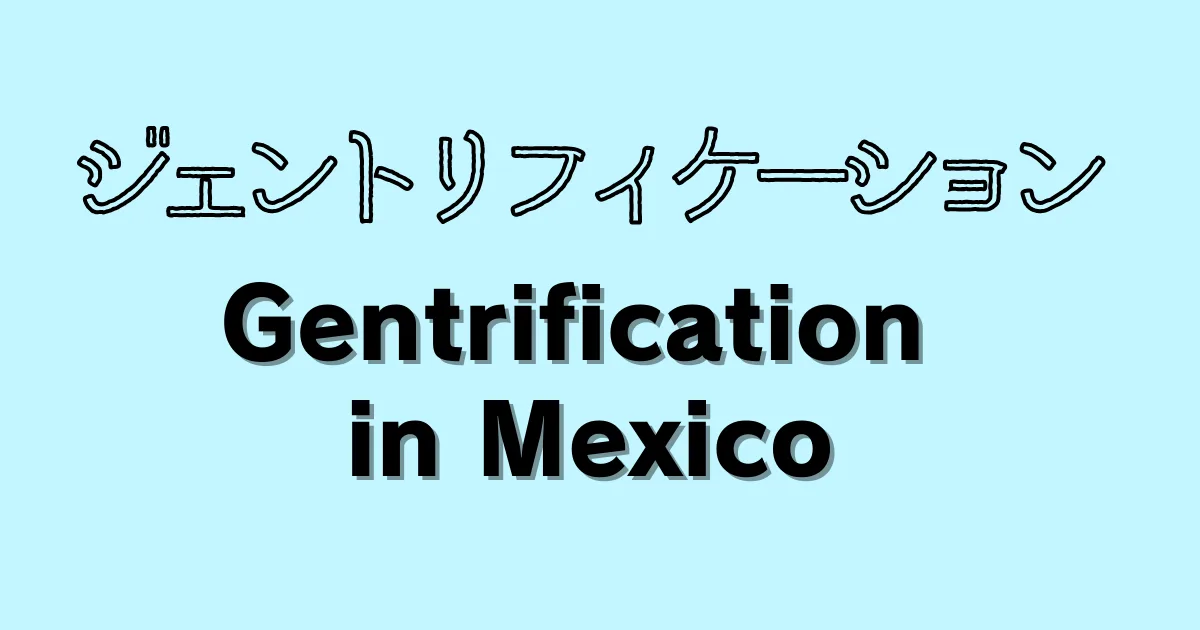
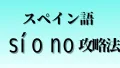
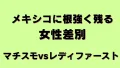
コメント